この記事でわかること
- ✅ 東大病院医師が逮捕された収賄事件の全容と構図
- ✅ 本来の研究支援である「奨学寄付金」が賄賂に化けた手口
- ✅ 逮捕された松原容疑者の不正な利益の総額とその他の手口
- ✅ 国立大学病院の医師に適用される「みなし公務員」の法的責任
- ✅ 今回の事件が示す大学病院の構造的な闇と再発防止の課題
2025年11月19日、日本の最高峰の医療機関の一つである東京大学医学部附属病院の医師が、警視庁に収賄容疑で逮捕されるという衝撃的なニュースが報じられました。
逮捕されたのは、医学部准教授を兼任していた松原全宏容疑者(53)です。
この事件の悪質性は、賄賂の提供が露骨な現金授受ではなく、大学の教育・研究を支援するはずの「奨学寄付金」という、極めて巧妙な形で行われていた点にあります。
長年、医療業界の不正を追ってきたジャーナリストとして、この事件の深層と、日本の大学病院が抱える構造的な闇を徹底的に解説します。
1. 事件の構図と容疑の概要
今回の事件は、国立大学病院の医師が、その職務権限を利用し、特定の業者に便宜を図る見返りに不正な利益を得たという、典型的な贈収賄事件です。
収賄側に東大病院の医師、贈賄側に都内の医療機器メーカーの社員という構図が明らかになっています。
1-1. 逮捕された容疑者と容疑
事件の主要容疑者と容疑の概要
- ✅ 収賄側は東大病院医師の松原全宏容疑者(53)
- ✅ 贈賄側は都内医療機器メーカー社員の鈴木崇之容疑者(41)
- ✅ 容疑は収賄罪と贈賄罪の適用
- ✅ 松原容疑者は「みなし公務員」として立件
松原容疑者は、担当する医療分野における医療機器の選定や使用について、強い裁量権を持つ立場でした。
贈賄側の鈴木容疑者は、自社製品を東大病院で優先的に使用してもらうことを目的に、松原容疑者に不正な利益を供与しました。
国立大学の医師は、国家公務員ではないものの、公的機関で職務を行うため、刑法上は「みなし公務員」とされ、収賄罪の適用対象となります。
関連記事:【解説】松原全宏容疑者ってなに者?東大病院准教授がなぜ収賄に関わったのか徹底調査
1-2. 賄賂の具体的な内容と時期
収賄容疑の核心となったのは、2021年9月頃と2023年1月頃の計2回にわたる金銭授受です。
鈴木容疑者は、松原容疑者の指示に基づき、東大病院の「奨学寄付金」の専用口座に、1回あたり40万円、合計80万円を振り込ませました。
松原容疑者は、この寄付金80万円のうち、約70万円を自己の研究費や活動費として不正に利用した疑いが持たれています。
2. 奨学寄付金が「賄賂」に化けた巧妙な手口(第三者供賄)
なぜ、公的な手続きを経る「奨学寄付金」が、刑法上の「賄賂」と認定されるのでしょうか。
ここに、大学病院が抱える寄付金運用の盲点と、贈賄側の巧妙な意図が見て取れます。
2-1. 第三者供賄という手口
松原容疑者が直接、業者から現金を受け取ったわけではありません。
贈賄側が、公務員(松原容疑者)が指定する第三者(東大病院の寄付金口座)に賄賂を供与する行為は、刑法上の「第三者供賄」に該当します。
この手口は、金銭の流れを複雑にし、賄賂性を隠蔽する目的で使われることが多く、過去の大学病院の贈収賄事件でも確認されています。
2-2. 奨学寄付金の「裁量権」が悪用の温床に
奨学寄付金が賄賂と認定される構造
- ✅ 寄付金は「研究室」や「講座」に紐づいて振り込まれる
- ✅ 教授・准教授などの責任者に実質的な裁量権がある
- ✅ 裁量権の範囲内で私的な利益のために使われたと認定
- ✅ 不正な便宜供与の「対価性」が明確になった
奨学寄付金は、基本的に寄付を受けた研究室や講座の教育・研究活動に資する目的で使われます。
しかし、その使途の判断には、松原容疑者のような責任者の裁量が大きく働きます。
警視庁は、松原容疑者がこの裁量権を利用し、寄付金の一部または全部を自身の私的な活動や研究グループの運営費に充てたことで、賄賂として成立すると判断したのです。
つまり、形は大学への寄付でも、実態は特定の医師への利益供与であり、見返りとの「対価性」が認められたことが立件の決め手となりました。
3. 不正の深層:賄賂は80万円だけではない
今回の捜査では、奨学寄付金80万円の授受が容疑の核となっていますが、警視庁は松原容疑者がメーカー側から受け取った不正な利益はさらに多額に上るとみています。
これは、単なる寄付金悪用にとどまらない、継続的かつ常習的な不正行為があった可能性を示唆しています。
3-1. 30万円相当の商品購入代行
報道によると、松原容疑者は寄付金とは別に、贈賄側のメーカー社員に対し、30万円相当の商品を自身のために購入させ、その費用を業者に負担させていた疑いが浮上しています。
これは、松原容疑者がメーカーを私的な「財布」や「便利屋」のように利用していた実態を物語っています。
この金銭の流れもまた、医療機器の優先使用という便宜供与の対価であったとみられています。
3-2. 不正利益の合計額と悪質性
松原容疑者が享受した不正な利益(概算)
- ✅ 奨学寄付金ルート(利用分)約70万円
- ✅ 商品購入代行費用約30万円
- ✅ 捜査中の他の不正な金銭提供約50万円
- ✅ 不正利益の合計は少なくとも150万円に上る可能性
寄付金と商品代行費用を合わせると、松原容疑者が受け取った不正な利益は既に100万円を超えています。
警視庁の今後の捜査次第では、贈賄側のメーカーだけでなく、他の医療機器メーカーとの同様の取引が明らかになる可能性も否定できません。
東大病院という最高学府の医師が、長期にわたり倫理観を欠いた不正行為を繰り返していたとすれば、その社会的影響は計り知れません。
4. 「みなし公務員」の重い責任と法的判断
国立大学が法人化された後、大学病院の医師は公務員ではなくなりましたが、その職務の公共性・公正性の観点から「みなし公務員」として収賄罪が適用されます。
この制度は、医療費や税金で運営される公的機関での不正を厳しく取り締まるためのものです。
4-1. 過去の判例と今回の立件
大学病院の医師による奨学寄付金を巡る収賄事件は、近年、散発的に発生しています。
例えば、2021年には三重大学病院の教授が贈収賄で逮捕・起訴され、有罪判決を受けています。
この三重大学のケースでも、奨学寄付金が第三者供賄と認定されており、今回の東大病院の事件も、この判例に沿った立件とみられています。
東大という日本最高峰の学府の医師が逮捕されたことで、医療界全体に対し、コンプライアンスの徹底が改めて求められることになります。
4-2. 松原容疑者と大学の倫理規定
東京大学は、教員に対して高い倫理規定を定めています。
特に、外部の企業との金銭授受や利益相反行為については、厳格な届出義務と承認プロセスが設けられています。
松原容疑者がこれらの規定を遵守していたか、あるいは意図的に回避していたのかも、大学側の調査の焦点となるでしょう。
5. 東大病院の対応と大学医療の構造的な闇
今回の事件は、東大病院という日本の医療界の象徴ともいえる組織で起きただけに、その影響は甚大です。
東大は、国民の信頼を回復するため、厳格な再発防止策を講じる責務があります。
5-1. 東京大学の緊急対応
松原容疑者の逮捕を受け、東京大学は即座に事実関係の調査委員会を立ち上げました。
大学側は、「誠に遺憾であり、国民の皆様に深くお詫び申し上げる」とする公式の謝罪コメントを発表しています。
松原容疑者は、逮捕と同時に職務停止処分を受ける見込みで、調査結果によっては懲戒解雇などの厳正な処分が下される可能性が高いです。
5-2. 医療機器選定における「権限の集中」
大学病院における医療機器の導入や使用は、特定の診療科のトップや影響力のある医師の意見が強く反映されます。
松原容疑者も、その専門分野において決定的な影響力を持っていたとみられ、ここにメーカーが付け入る隙がありました。
この権限の集中構造こそが、贈収賄事件の構造的な闇であり、寄付金が悪用される背景にあります。
選定プロセスの透明化と外部監査の強化が、今後の再発防止の鍵となります。
6. まとめ:問われる医療界の倫理観
今回の東大病院医師の収賄事件は、単一の不正行為にとどまらず、国立大学病院のガバナンスと倫理観が根底から問われる事態です。
特に、「奨学寄付金」という学術支援の美名を借りた不正の手口は、医療界全体への信頼を大きく傷つけました。
警視庁による捜査の徹底は、聖域とされてきた大学病院の不正にメスを入れる重要な一歩となります。
今後、贈賄側のメーカーの責任や、不正の全容解明に向けた司法の判断が注目されます。
6-1. 再発防止への提言
再発防止に不可欠な改革
- ✅ 奨学寄付金の使途の透明化と第三者による監査の義務付け
- ✅ 高額医療機器の選定における複数部署による合議制の徹底
- ✅ 医師とメーカー間の利益相反に関する厳格な罰則規定の導入
- ✅ 全職員に対する「みなし公務員」としての倫理研修の強化
国民の生命と健康を守るべき最高学府の病院が、不正の温床であってはなりません。
今回の事件を教訓として、医療界全体が倫理と透明性を取り戻すための、徹底した自己改革が求められます。

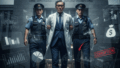
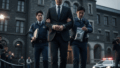
コメント