この記事でわかること
- ✅ ポッキーの日の売り場が異様に盛り上がる理由
- ✅ 巨大な「ポッキータワー」が完成するまでの緻密な計画
- ✅ 設営当日の店員たちの知られざる苦労と技術
- ✅ タワー崩壊の恐怖と、当日の「補充地獄」の実態
- ✅ コンビニとスーパーで売り場戦略が異なる背景
1. 11月11日という「戦場」:小売店がポッキーの日にかける情熱
なぜ、小売店はこれほどまでにポッキーの日に情熱を注ぐのでしょうか。それは、この日が単なる「お菓子を売る日」ではないからです。
1-1. なぜポッキーの日はこれほど盛り上がるのか?
1999年(平成11年)に制定されたこの記念日。今や国民的行事の一つと言っても過言ではありません。その背景には、メーカーである江崎グリコの巧みな戦略があります。
「1」が並ぶ形状のキャッチーさ。そして、「シェアハピネス」というコンセプト。これが、SNS時代と完璧に融合しました。友人とポッキーをシェアする姿を投稿する。この文化が定着し、消費者が自ら宣伝塔となる構造が生まれました。メーカーはテレビCMや大型キャンペーンでこれを後押しします。結果、11月11日は「ポッキーを買う日」として強力に刷り込まれました。
1-2. 小売店にとっての「ポッキーの日」の重要性
小売店にとって、この日は年に一度の「ビッグチャンス」です。クリスマスやバレンタインデーに匹敵する、お菓子カテゴリの最重要商戦日となります。
この日の売り場作りは、店の「やる気」を示すバロメーターです。華やかな売り場は、顧客の購買意欲を刺激します。それはポッキーだけに留まりません。「ついで買い」を誘発し、店全体の売上を押し上げる効果が期待できます。ポッキーを買いに来た客が、飲み物や他の食品も買っていく。この相乗効果こそが、店側の最大の狙いなのです。
1-3. 売り場担当者のプレッシャー
しかし、その裏で売り場担当者は大きなプレッシャーと戦っています。
まずは、競合店との戦いです。「あそこのスーパーよりすごいタワーを作れ」。そんな無言の圧力がかかります。SNSで「〇〇店のタワーがすごい」と拡散されれば、それは店の名誉となります。
さらに、本部やチェーン全体での売上目標があります。この日の売上は、店舗の評価に直結します。担当者は「絶対に失敗できない」という重圧の中、売り場作りに挑むのです。
2. 「ポッキータワー」設計図:華麗なるオブジェの企画段階
あのタワーは、決して一朝一夕にできるものではありません。その設営には、数週間前から始まる周到な準備と、緻密な計算が存在します。
2-1. 戦いは数週間前から始まっている
戦いの火蓋は、10月中旬頃に切られます。メーカーや本部から、今年の「販促企画書」が店舗に届きます。そこには、キャンペーンの詳細や景品の情報。そして、推奨される陳列(タワー)の見本写真が添付されています。
店長や売り場担当者は、この資料を睨みます。そして、自店のスペースと人員を考慮し、計画を練り始めます。「今年はどんなタワーで勝負するか」。ここから、目に見えない戦いが始まるのです。
2-2. 発注量のジレンマ:「欠品」と「過剰在庫」の狭間で
タワー設営における最大の難関。それが「発注」です。担当者は、究極の二択を迫られます。
「欠品」は、小売業における最大の罪とされます。せっかく来た顧客が買えない。これは、売上機会の損失であり、顧客の信頼を失う行為です。特に11月11日当日の欠品は、絶対にあってはなりません。
しかし、「過剰在庫」もまた地獄です。売れ残った大量のポッキー。それはバックヤードを圧迫し、最終的には値引き販売されます。店の利益を圧迫する元凶となるのです。
現役コンビニ店員 A氏の証言
「ポッキーの日の発注は本当に胃が痛いです。当日に売り切れてもダメ。12日に残りすぎてもダメ。まさに『チキンレース』ですよ。過去3年間の売上データと、SNSの盛り上がりを毎日チェックします。そして、最後は『勘』で発注ボタンを押すんです。あの瞬間は、いつになっても慣れませんね。」
担当者は、昨年のデータ、天候、曜日配列。あらゆる要素を分析し、最適な発注量を見極めようと苦心します。
2-3. 設計図は誰が描くのか?
タワーの設計図は、複数の人間によって描かれます。
一つは、メーカーの営業担当(ラウンダー)です。彼らは各店舗を巡回し、自社製品をアピールします。ポッキーの日が近づくと、彼らはタワーの見本写真やPOP(販促物)を持参します。「この設計なら売れますよ」と、設営のサポートを申し出ることもあります。
もう一つは、店舗のベテラン店員の経験です。長年売り場を見てきた彼らは、「店のどの場所が一番目立つか」「顧客の動線はどうなっているか」を熟知しています。彼らの「職人技」とも言える感覚が、設計図に反映されます。
最終的には、店のスペースという現実的な制約の中で。メーカーの提案と、店員の経験が融合し、その店独自の「設計図」が完成するのです。
3. 【裏側潜入ルポ】「ポッキータワー」設営当日のドキュメント
企画と発注を経て、ついに設営当日(多くの場合は11月10日の夜)を迎えます。ここからは、時間との戦いです。
3-1. Xデー前夜:閉店後の静かなる激闘
顧客が寝静まった深夜。閉店後のスーパーや、客足が途絶えた深夜のコンビニ。そこで、静かなる激闘が始まります。
まず、バックヤードに山積みされたポッキーの段ボール。これを、売り場の設営場所まで運び出します。その量は、数百箱に及ぶことも珍しくありません。この単純な運搬作業だけで、数時間が経過することもあります。
通常の棚を移動させ、タワーを建てるスペースを確保します。そして、清掃を終えた床に、設計図通りに土台を組み始めます。
3-2. ステップ1:土台作りと重心の確保
タワー設営で最も重要な工程が「土台作り」です。
タワー設営の鉄則:安定性の確保
タワーは、下部が最も重くなるように設計されます。大袋のアソートパックや、重いフレーバー(アーモンドクラッシュなど)を最下層に配置します。重心を低くすることで、安定性を確保するのです。
また、全ての箱に中身が入っているとは限りません。特に巨大なタワーの中心部や上部には、「ダミー」と呼ばれる空箱が使われることもあります。これは、重量を軽くし、崩壊リスクを減らすための重要な技術です。顧客が手に取る部分だけを本物の商品にするのです。
箱を一つひとつ、歪みがないか確認しながら積み上げます。少しのズレが、後で大きな崩壊に繋がるため、作業は慎重を極めます。
3-3. ステップ2:積み上げの技術と「魅せる」陳列
土台が完成したら、次は「魅せる」工程です。ここで、担当者のセンスが問われます。
最も目立つのは、やはり定番の「赤箱」です。この赤色をいかに効果的に配置するかが、タワーの印象を決定づけます。赤箱の間に、アクセントとして「極細」の黒や、「アーモンドクラッシュ」の金色を配置します。
顧客がどの方向から来ても美しく見えるよう、360度意識して積み上げます。商品の「顔」(パッケージ正面)が、常に見えるように調整するのは、熟練の技が必要です。この作業は、まるで巨大なパズルを組み立てるかのようです。
3-4. 崩壊の恐怖:店員が語る悪夢の瞬間
タワー設営は、常に「崩壊」のリスクと隣り合わせです。店員たちは、過去の悪夢を語ります。
元スーパー店員 B氏の証言
「深夜3時頃、タワーが9割完成した瞬間でした。作業台車が少し接触したんです。次の瞬間、スローモーションのようにタワーが崩れ落ちました。数百箱のポッキーが床に散乱し、何箱かは潰れてしまいました。あの時の絶望感と、虚しい箱の音は忘れられません。結局、開店時間ギリギリまで復旧作業に追われました。」
「日中の恐怖は、お子様連れのお客様と、買い物カートです。子供が下の方の箱を抜こうとしたり、カートが激突したり。その度に肝を冷やします。小さな地震でも、心臓が止まりそうになりますよ。」
設営の苦労を知っているからこそ、店員はタワーの安全に神経を尖らせるのです。
4. タワーだけではない!ポッキーの日売り場の緻密な戦略
11月11日の売り場戦略は、タワーだけではありません。その周辺には、顧客の財布の紐を緩めるための、様々な仕掛けが施されています。
4-1. 関連陳列(クロスマーチャンダイジング)の罠
タワーの隣に何が置かれているか、注目してみてください。そこには、店の明確な意図が隠されています。
ポッキーの「相棒」たち
ポッキーと一緒に買われやすい商品。これを「クロスマーチャンダイジング(関連陳列)」と呼びます。店側は、これらの商品をポッキーのすぐ隣に陳列します。
- ✅ 飲料:コーヒー、紅茶、牛乳、ココアなど。「温かい飲み物とご一緒に」と提案。
- ✅ アイスクリーム:特にバニラアイス。「ポッキーを刺して楽しもう」と提案。
- ✅ パーティグッズ:紙皿、紙コップなど。「ポッキーパーティー」を演出し、単価アップを狙う。
顧客は「あ、コーヒーも切れそうだった」と、無意識のうちにカゴに入れてしまいます。これが、客単価を上げるための高度な売り場戦略なのです。
4-2. POPと景品が織りなす「買わせる」仕掛け
タワーには、様々なPOP(販促物)が飾られています。「本日限り!」「11月11日」といった派手な告知。これらは顧客の「今買わなければ」という緊急性を煽ります。
さらに強力なのが「限定景品」です。「対象商品2個購入で、オリジナルチャームプレゼント!」。この「おまけ」戦略は、特にコンビニで絶大な効果を発揮します。景品が欲しいがために、買う予定のなかった人まで購入に至るのです。
4-3. なぜコンビニとスーパーで売り場が違うのか?
ポッキーの日の売り場は、業態によって明確な違いがあります。
コンビニエンスストアは、客層が若く、単身者が中心です。そのため、「限定景品」や「コラボ商品」をフックにします。売り場スペースが狭いため、タワーは比較的小型ですが、レジ前などの一等地に設置し、即時消費を狙います。
一方、スーパーマーケットは、ファミリー層がメインターゲットです。「みんなでシェア」を打ち出し、「9袋入りシェアハピパック」などの大袋・アソート商品をタワーの土台にします。景品よりも「レシート応募キャンペーン」など、家族で楽しめる企画が中心となります。タワーも、売り場の広さを活かした巨大なものが作られる傾向にあります。
5. 当日の悲劇:タワー完成は「終わり」ではなく「始まり」
11月11日、午前0時。あるいは早朝の開店時間。華々しくタワーがお披露目されます。しかし、店員たちの本当の戦いは、ここから始まります。
5-1. 開店と同時に始まる「補充地獄」
あの巨大なタワーは、単なるオブジェではありません。それは、「売るための在庫」そのものです。
開店と同時に、顧客が次々とタワーから商品(ポッキー)を抜き取っていきます。すると、タワーは当然、形が崩れていきます。美しいタワーの形状を維持するため、店員は即座に商品を補充しなければなりません。
「売れる」→「補充する」→「売れる」→「補充する」。この無限ループが、11月11日の閉店まで続くのです。バックヤードと売り場を何十往復もする。これが「補充地獄」と呼ばれるゆえんです。
5-2. 店員C氏(ドラッグストア)が語る「11月11日のリアル」
ドラッグストアも、今やお菓子販売の激戦区です。ある店員は、当時の様子をこう語ります。
店員C氏(ドラッグストア勤務)の回想
「あの日は、朝から晩までポッキーを触っていた記憶しかありません。うちはレジが2台しかないのに、お客様のほとんどがポッキーをカゴに入れている。レジが混む。レジ応援に呼ばれる。レジが終わると、タワーのポッキーがごっそり無くなっている。慌ててバックヤードに取りに行く。
その繰り返しです。世間が『シェアハピ』で浮かれている中、こっちは『シェア(分担)』と『ハピネス(とは程遠い疲労)』でした。もちろん、売れるのは嬉しいんですけどね。」
5-3. 崩壊リスクとの戦い(再び)
設営時の崩壊リスクは、むしろ当日のほうが高いと言えます。多くの顧客がタワーに触れるからです。
特に危険なのは、下の方の商品が売れた時です。土台が不安定になり、タワー全体のバランスが崩れやすくなります。店員は、補充の際に商品の位置を微調整し、重心を常に安定させるという、高度な技術を要求されます。
「お客様、危ないですから上からお取りください!」。そんな声が、売り場に響き渡ることも珍しくありません。
6. 11月12日、祭りの後:タワー解体と現実
嵐のような11月11日が過ぎ去ると、12日の朝が訪れます。そこには、祭りの後の静けさと、新たな現実が待っています。
6-1. 儚きタワーの最期
あれほど壮麗だったポッキータワーも、その役目を終えます。多くの店では、11日の閉店後、あるいは12日の早朝に解体作業が始まります。
あれだけ苦労して積み上げた箱が、今度はあっという間に崩されていきます。その光景には、一抹の寂しさが漂います。解体されたポッキーは、お菓子コーナーの「平場(ひらば)」と呼ばれる通常の棚に、静かに戻されていきます。
6-2. 在庫との戦い(第二章)
ここで、発注担当者が再び試練に直面します。「在庫」です。
定番の赤箱は売れ行きが良いものの、限定フレーバーや大袋は、意外と残ってしまうことがあります。発注量が多すぎた場合、バックヤードは「ポッキーの壁」と化します。
ここから、賞味期限との戦いが始まります。売れ残った商品は、まず目立つ場所で「見切り品」として値引きされます。それでも売れなければ、さらに割引率が上がります。タワー設営の苦労は、こうして「在庫処分」の苦労へと姿を変えるのです。
6-3. 店員たちの本音と達成感
これほど過酷なポッキーの日。店員たちは、何を思うのでしょうか。
祭りを終えた店員たちの本音
「正直、二度とやりたくないと思うほど疲れます。」
「でも、自分たちが作ったタワーを見て、お客様が『わぁ、すごい!』と喜んでくれる顔を見ると、疲れも吹き飛びます。」
「SNSで『近所の〇〇店、タワーが芸術的』と写真が上がった時は、バイト仲間とガッツポーズしました。」
「目標売上を達成した時の達成感は、何物にも代えがたいですね。」
「そして、12日になると『来年はもっとすごいタワーを作ってやろう』と、なぜか思ってしまうんです。」
疲労困憊の先に待っている達成感。それこそが、彼らを突き動かす原動力なのかもしれません。
7. まとめ
11月11日、ポッキーの日。私たちが目にする華やかな売り場。
その裏側には、緻密な販売戦略があります。そして、プレッシャーと戦いながら売り場を創り上げる店員たちの、知られざる情熱と苦労があります。
あの「ポッキータワー」は、単なる商品の山ではありません。それは、小売業のプライドと、店員たちの汗と涙が積み上がった結晶なのです。
今日、あなたがポッキーを手に取るとき。その箱を積み上げた「誰か」の存在に、少しだけ思いを馳せてみてはいかがでしょうか。


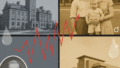
コメント