この記事でわかること
- ✅ 浅野真澄氏の「黒歴史」とされる出来事の全体像
- ✅ エッセイ『逝ってしまった君へ』が生まれた背景となる友人の死
- ✅ コンテンツ配信サービス「Cakes」が起こした連載中止騒動の詳細
- ✅ 浅野氏が連載中止に至るまでに受けた不誠実な対応
- ✅ 困難を乗り越え、いかにして作品が書籍化されたか
1. 浅野真澄の「黒歴史」が指す複合的な困難
声優として活躍する浅野真澄氏が、文筆家「あさのますみ」名義で発表した作品の裏側には、一部で「黒歴史」と呼ばれる一連の複合的な困難が存在しています。この「黒歴史」は、単なる過去の失敗や恥ずかしい出来事を指すものではありません。むしろ、極めて個人的で痛ましい喪失体験と、その作品が社会的な炎上騒動に巻き込まれたという、公私にわたる苦難の歴史を意味します。この出来事を深く理解することは、現代のメディアと個人の創作活動の関係を考える上で重要です。
「黒歴史」とされる期間は、大切な友人の死を機に執筆を始めた時期から、コンテンツ配信サービス「Cakes」での連載が不当に取り消され、最終的に書籍化を果たすまでの期間を指します。彼女は、この経験を通じて、作家として、そして一人の人間として、メディアの非情さと向き合うことになりました。
2. 創作の原点となった大切な人との永遠の別れ
一連の出来事の起点となったのは、浅野氏にとって非常に大切な人物の死でした。それは大学時代からの友人で、彼女にとっては「初めての恋人」でもあり、別れた後も変わらずかけがえのない友人であり続けた人物です。この友人は、2019年1月に自ら死を選ぶ(自死)という形で、突然この世を去りました。この事実は、浅野氏に深い悲しみと受け入れがたい衝撃を与えました。
亡くなった友人は、明るく社交的で語学も堪能な優れた人物でした。しかし、その裏で鬱病を患い、自身の存在価値に対する自信を失っていたことが、後のエッセイで明かされます。この「能力はあるが、存在に自信がない」という友人の苦悩は、現代社会の生きづらさを象徴しているとも言えます。浅野氏は、この「混沌とした気持ち」を整理し、誰にも話せなかった想いを文章にするという形で、悲しみに向き合うことを決意しました。
2.1. 執筆動機と「逝ってしまった『君』への手紙」
浅野氏が書き始めたのは、亡き友人への「手紙」という形式でした。このエッセイは、自死によって遺された人々の複雑な感情、遺品整理、そして「なぜ」という問いに答えを求め続ける苦闘が綴られています。この作品は、2020年3月に「note」で公開されると、その真摯な筆致と重いテーマにもかかわらず、大きな反響を呼びました。この作品は、後に「cakesクリエイターコンテスト2020」で受賞するに至り、Cakesでの連載へと繋がります。
エッセイの核となったメッセージ
- ✅ 亡くなった友人の抱えていた「存在への自信のなさ」という苦悩
- ✅ 自死で大切な人を失った遺族・友人の深い悲しみと葛藤
- ✅ 悲しみの中で見つける「自分を肯定する強さ」と新たな人生の価値観
3. 炎上サービス「Cakes」との不運な遭遇
浅野氏の創作活動の次なる段階は、コンテンツ配信サービス「Cakes」での連載でした。しかし、この連載は、Cakes側の相次ぐ炎上騒動に巻き込まれる形で、悲劇的な結末を迎えることになります。結果的に浅野氏は、この炎上サービスの「被害者」の一人として知られることとなりました。
3.1. 相次ぐCakesの炎上と連載への影響
浅野氏の連載開始が目前に迫った2020年秋、Cakesは立て続けに大きな炎上を引き起こします。具体的には、DV被害者を軽視すると受け取られかねない人生相談記事や、ホームレスを蔑視するような表現を含む記事が公開され、社会的な批判が殺到しました。これらの炎上は、Cakesの編集体制の未熟さと倫理観の欠如を露呈させるものでした。浅野氏の作品自体には問題がありませんでしたが、炎上の余波が彼女の連載にも及び始めます。
3.2. 運営側による「フィクション化」提案の衝撃
最初のDV関連記事の炎上後、Cakes側は浅野氏に対し、彼女の実話に基づくエッセイを「フィクションという体裁にしませんか」と提案しました。これは、炎上を恐れた運営側の保身と見られる対応であり、浅野氏に極度の精神的苦痛を与えるものでした。彼女にとって、それは亡き友人の「死」の重みや自身の真摯な想いを、メディア側の都合で「軽んじられる」と感じさせるものでした。
4. 連載の不当な取り消しと不誠実な対応の詳細
二度目の炎上(ホームレス蔑視記事)が発生した後、事態は決定的な局面を迎えます。Cakesの運営元であるnoteの執行役員から、浅野氏の連載が「掲載できない」という一方的な通告があったのです。ここからのCakes側の対応は、「黒歴史」と称される所以となった、極めて不誠実な連鎖でした。
4.1. 翻弄された連載取り消しの理由
連載取り消しの際、Cakes側は当初、「炎上のせいではない」と強調しました。その代わりに挙げられた理由は、「自殺というテーマは非常にセンシティブに扱われているため、内容に問題があった」というものでした。しかし、この主張は、炎上による萎縮が根本原因であり、自死をテーマにした作品を不当に排除するための言い訳であると、多くの識者から批判されました。浅野氏は、この「センシティブだから」という理由が、何をどうすれば回避できたのか不明であり、誠意を欠くと感じています。
4.2. 屈辱的な「原稿の買い取り」提案
さらに、運営側は連載取り消しの通告とともに、既に執筆された原稿を「一本7,000円」という極めて安価な金額で買い取るという提案をしました。これは、浅野氏が深い悲しみを乗り越えて綴った作品の価値を、非常に低く見積もった行為であり、作家に対する敬意の欠如を示すものでした。この提案は、浅野氏にとって二重の屈辱となり、事態の深刻さを世に知らしめることになりました。
連載中止騒動で露呈した問題点
- ✅ 複数の炎上による運営・編集体制の崩壊
- ✅ 作品のテーマ性ではなく炎上回避を優先した保身的な判断
- ✅ 作家への一方的な通告と低額な原稿買い取りの提案
- ✅ 作家の個人的なトラウマを軽視するような不誠実な対応
5. 浅野真澄の「告発」と誠実な「和解」への道
Cakes側からの不当な連載取り消しと不誠実な対応を受け、浅野氏は沈黙を選ぶことなく、一連の経緯を記したnote記事「cakes炎上と、消滅した連載」を公開しました。これは、自身の創作活動のリスクを覚悟した上での、誠実な告発でした。この告発は、世論を味方につけ、Cakes運営元に対する強い批判を巻き起こしました。
5.1. 要求した謝罪文の「7つの条件」
浅野氏がCakes側に求めたのは、単なる金銭的な補償ではなく、誠意ある公式な謝罪でした。彼女は、Cakes側が謝罪文に含めるべき内容として、以下の7つの明確な条件を提示しました。これは、再発防止と作家の尊厳回復を目的としたものであり、彼女のジャーナリスティックな視点が垣間見えます。
- 浅野真澄さんの名前を明記すること。
- 編集部の未熟さに起因する炎上が連載消滅の原因であること。
- 炎上が原因であったにもかかわらず、当初「炎上のせいではない」と虚偽の説明をしたこと。
- 担当編集がOKを出した原稿に対して、業界の常識を無視して書き直しを要求したこと。
- 浅野さんと友人の遺族に多大な精神的負担をかけたこと。
- 今後再発防止に努めること。
- これらの条件を全て含んだ公式な謝罪文を掲載すること。
Cakes側は、この全ての条件を受け入れ、浅野氏との間に「和解」が成立しました。この対応は、メディア側が作家に対し責任を負うという点で、大きな意味を持つものでした。
6. 「黒歴史」を昇華させた『逝ってしまった君へ』の書籍化
Cakesでの連載は消滅しましたが、浅野氏の作品の価値は出版社によって正しく評価されました。このエッセイは、小学館の編集者の声かけにより、大幅な加筆が施された長編エッセイとして、2021年に『逝ってしまった君へ』(あさのますみ名義)として書籍化されました。
6.1. 書籍に込められたメッセージ
書籍化された作品には、Cakes騒動で得た「メディアと個人の関係」に対する新たな視点も加わっています。この作品は、単なる個人的な追悼文に留まらず、「自死遺族」が抱える共通の苦悩、そして、他者の無責任な言動から自分自身を守るための「心の盾」を見つけ出す過程を描いています。浅野氏は、この本を通じて、「たった一つのものさしで自分を測ることに意味はない」という、自己肯定感の重要性を強く訴えかけています。
6.2. 著作権と二次利用に関する教訓
この騒動は、作家とプラットフォームの関係、特に著作権や二次利用に関する契約の重要性についても、大きな教訓を残しました。浅野氏は、自身の経験を共有することで、他のクリエイターに対し、プラットフォームとの契約内容を慎重に確認するよう促しています。この一件は、ウェブ時代の創作活動におけるリスク管理の必要性を浮き彫りにしました。
まとめ
浅野真澄氏の「黒歴史」は、彼女が声優という枠を超え、文筆家として社会的なメッセージを発信する過程で直面した避けがたい試練でした。大切な友人の自死という深い悲しみと、炎上によって機能不全に陥ったメディアからの不当な扱いという、二重の苦難でした。しかし、浅野氏はその都度、誠実な対応と冷静な分析によって問題を乗り越え、結果として普遍的なメッセージを持つ作品を世に送り出しました。この一連の経緯は、表現者が直面する現代の課題を示す重要な事例として、今後も語り継がれるでしょう。

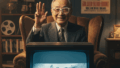

コメント